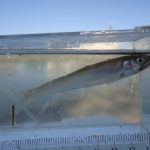先週末縮み上がるような寒さの中仕掛のテスト兼ねましてまたまたタナゴ釣りに出動しました。
仕掛のテスト結果はあまり良好とはいえませんでしたが越冬ポイントに集まりつつ有るタナゴはほどほどの釣果がでました。
これからは越冬の為に減水した水路の特定の小場所にタナゴが集まりつつ有るので、流れが緩るく日当たりのいい他所より水深の有りそうなポイントさえ見つかれば初心者でも入れ食いの楽しい一日が過ごせる可能性が高まってきます。
私も昨年タナゴ釣りを始めた当初、運良く好ポイントにて数釣りを経験してからどっぷりはまってしまいました。
自身の寒さ対策さえすれば冬場であろうとタナゴは釣れる魚ですので興味有れば始めていただければと思います。
では釣行当日の話を始めてみます。
当日の様子
当日はここ最近でもとりわけ気温が低い予想で最高気温でも一桁第との予報となつてました。私は大阪在住なのですが朝方玄関先でもあまりの寒さに震えあがってしまいました。
少しテンションは下がりぎみとなってしまいましたが、昨日晩にこしらえた仕掛けの具合もみたく、短時間で切り上げる予定ででかけました。
久方ぶりにワークマンイージスの出番となりましたが、暖かさは昨年経験済みです。
現場には遅めに到着しましたが風裏の為辛抱出来ない程では有りません。

まずはじっくり水路の様子など観察です。
この場所は水門脇で昨年の冬場と同じく魚影は濃く多くの魚が右に習えで大小集団で泳いでいました。
おそらくはモロこやクチボソなどの細長組であろうとおもいます。

浅瀬にはメダカサイズがひとかたまりでむれています。
何の稚魚かは特定出来ませんがそのままこの辺りで越冬する可能性は大きいです。
このポイントはまずは今冬期もタナゴ越冬ポイントの候補で決定です。

ときたま単独で変則的な動きをしウロウロしているのは間違いなくバスです。
寒さに負けず今も元気な様ですがさらに水温がさがれば動けなくなり落ちつくはずです。
元気な獲物は追いきれず捕獲できないようですが弱った小魚を探しているのでしょうか。
この様な浅く狭いキャパの中で冬を乗り越えられるかは疑問ですが私としてはあまり歓迎はできません。
そしてこの様な状況でもタナゴは居るのかとの事ですが、当水路では確実にいます。
この季節夏から秋の様な大型狙いはできませんし、非常に微妙な当たりとなり難し苦なるのは間違い有りませんが、所々のボイントに分散して越冬の為集まりだしています。
このようなポイントに当たれば適切な仕掛を(特に針は 極みタナゴなど特化した針が必ず必要です)用いれば冬場であろうと初心者でもタナゴを釣り上げる事が可能です。
そして当日も岸際間近に倒れこんだ枯れ草の下に多数の魚が見え隠れしていましたがおそらくタナゴ達です。
どうやら仕掛けを投入できるボイントまで誘い出す必要がありそうです。
グルテン餌の出番ですが、最近は少しニンニク臭の強い「野釣りグルテン」を使用しています。
これを多めに作り枯れ草間際のピンポイントに団子にして数個放り込み一旦釣り座を離れてしばらくコーヒータイムです。
しばらくしてから様子を伺うとおチビさん達が団子周りに集まり出しています。
私の中では徐々に大きな魚へと活性が伝染していきいずれ群れ全体がわらわら集まり出すイメ-ジがあります。
しかし水温が低く活性の低いこれからの季節は、群れ全体の活性が上がるのはしばらく時間がかかります。
しばらくは餌の打ち込みとスカ当たりを繰り返し少し大きめの豆バラが針掛かりするのを待つ必要がありそうです。
当日の釣果は
まさに寒さにに耐えながらの辛抱の時間です。寒いからといつて岸際をウロウロすれば敏感な魚は警戒して引っ込んでしまいます。
一箇所に座しエンコスタイルで辛抱強く仕掛けを打ち込むこと半時間余り、やつとこさ針掛かりしました。

背びれに黒星、目玉周りが紅色の関東ではオカメとよばれているタイリクバラタナゴの幼魚ではっきり言えば外来種となりますが国産のバラタナゴと交配が進み今やハイブリッドが多数存在し見分けがたいと聞いています(タイバラの腹ビレの前縁には白い帯が見られるそうですが無い個体も存在するようで今や見分けが付きにくいそうです)
私は当ブログで豆バラといつていますが上記の様な非常に分かりやすい特徴が有ります。
そしてタイミングを逃さずテンポよくつりあげた結果が下記となりました。

ここらで寒さに負け2時間足らずでギブアップのため本日は終了としました。
自作仕掛の具合
ここで先頃作製しました自作仕掛けの使用の結果なのですが、あまりかんばしくない事になつてしまいました。当日のポイントは非常に浅めで、仕掛けをは底にひつぱられず横にひつたくられる様な当たりとなるためトンボが回転するというよりスライドする様な反応になり機能を果たす事が出来ませんでした。
トンボのバランスや左右の対称性などに問題ありと思われますが、自作の出来はまだまだの様でさらに改良が必要の様です。
たしかに当たりは比較的見易いですが当たりを回転して知らせるトンボの役割が果たせていません。
残念ですが今回は途中からトンボナシの予備の仕掛に変更しました。
今後もうしばらく研究して見ます。
帰路特効餌の採取
そして帰路途中の収穫としまして玉虫発見しました。
非常にきれいな柄となって寄生された穴も無いのでおそらく中身も大丈夫そうですので機会あれば使用してみます。
昨年城北のワンド裏では多数採取しましたがいまいちうまいこと使えていません。
この餌は当たり外れが大きく中で死滅していたり寄生されていたりでなかなか健康な状態の繭の採取の難しいです。
まだら柄のきれいな物や寄生の穴のない個体をより分けて採取する必要があります。
特に柿やサクラの木またはバラ課の枝などに多く張り付いているようですが、人に管理されている木が多く、がっちり枝に食い込んでいるため勝手に枝ごと採取するのはNGですのでなかなか集めるのが手間が掛かります。
今回は帰り際水路際の間伐された枯れ枝にたまたまぶら下がっているのを見かけラッキーでした。
幼虫の頃は毒虫として敬遠されれ駆除対象ですが、冬場に取れるマユは特効餌としてタナゴ釣りのファンには非常にうれしい収穫となります。
使い方は難易度が高そうですがいずれうまく使いこなせればと思っています。
まとめ
当日は気温こそ低いのですが比較的風の緩いポイントを選びましたので寒さを我慢しながらとりあえずは釣果を出しました。当日見かけた釣り人はタナゴ狙いだった様ですが渋さに負け即退散したみたいです。
おそらく私は懲りずに休みの度出掛けてしまう事確実ですが、とりあえずは釣行の様子は続けてブログにアップし続けるつもりです。
なお当日採取した玉虫の保管はどのようにするのがベストなのでしょうか。
あまり暖かい場所では羽化しそうで怖いし、冷蔵庫の野菜室などもっての他でばれれば非難ゴウゴウ確実でしょうから次回の釣行で即使用するのがいいかもしれません。
では本日はこの辺で終わりにしたいと思います。