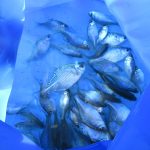前回タナゴ浮き試作してみましたが、作成途中に色々不具合ありました。
今回は少し前回の反省点をふまえ、少し作成の手順かえてみました。
また色塗り用には、ネット参考にしましてアイデアいただき、模型モーターで簡単な色塗り機作成してみました。
では今回の話始めてみます。
簡易色塗り機
前回浮き塗りの仕上げ時のライン入れにリューターの回転が速すぎとの話しましたが、対応するため、下記の簡易色塗り機作成してみました。ここらのアイデアは下記ネットから情報いただいただけです。
http://yamame110.ldblog.jp
アイデアがすばらしいです
同じように作製で揃えました材料は下記写真のとおり

①マブチ製DCモーター
3v直流DCモーターで私世代の元模型小僧だった方には懐かしいマブチ製です。
回転数は今一ピンとはこないですが負荷回転数が7500回転とのことです。
今回はあまり速度は必要ないのですが、ある程度指でおさえながら筆を当てる事になるので回転トルク(回転する力)が必要です。
今回は少しだけ上位の260RA選びました。(他に140や130も有り)
モーターの台座などは付属しています。
②タミヤ製電池ボックス
こちらはプラモ関係の最大手のタミヤ工作シリーズの製品となります。
単3二列直列の製品で スイッチ+コードが付属しています。
③低電圧DC回転制御基盤
こちらは通販バルク品で簡単な配線だけで直流のモーターや、電球などの電圧をボリュームで制御する基盤です。
説明など全くない袋入りの基盤ですがモーターからの2本と電池からの2本のコードネジ止めで固定するだけです。
④シャープペンのチャック部分
こちらは机の中に眠っていたお古で、分解して芯部分をカットしました。
これらしめて約1600円也で少し高めですが久しぶりの工作楽しみました。
ブログ読者の方から、リューターの制御に交流用の電圧制御基盤の情報いただきましたが、ハンダ付けなど私の手に余ると思われましたので今回はみおくりました。
情報ありがとうございました。
今回の工作では、特にシャープペンのチャック部分など私では思いつかない所ですので真似させていただきました。
諸先輩の着眼点がすごいと思います。
そして出来上がりましたのが下記写真です。

ボリュームで回転数が簡単に調整出来る様になりました。
こちらで最終的に墨ラインなどいれてみたいとおもいます。
成形加工手順変更
まずは6mmバルサ丸棒カット
0.8mmカーボン浮足さしこみ

カッターによる荒削り

ここまでは同じ
ここで先に斜めにパイプを差し込む穴を先にあけてしまいます。

成形後の穴あけ時にどうしても穴周りにバリ剥がれが出るからです。

そのまま80番で荒削り及び600番で仕上げ手前まで削ります。

ここで塩ビパイプを差し込みます。


余分目に差し込み、はみ出した部分に瞬間接着剤を塗り、パイプを引き戻して固定します。
ここでモタモタしますと瞬時に固定されてしまいますのである程度すばやくです。

後は両サイドのパイプをなるべくギリギリでカットして斜め穴の加工は終了

最後は今一度600番手で穴付近を削り平滑に近づけます。
ここでパイプ穴周りや浮足の付け根あたりの凹みなど極少量のレジンを盛り付け紫外線でかためてしまいます。
最終仕上げで1000番ほどでなめらかになるよう全体を磨いて成形は終了です。
塗装手順変更
実は先の試作の大失敗の話ですが、最終ウレタンコートが先の水性塗料を冒してしまつたみたいで部分剥がれが発生してしてしまいました。
ぼろぼろです(笑い)
水性系の着色の上塗りに油性ウレタン使用したのが原因かもしれませんし、乾燥時間が短すぎたのか思考錯誤中です。
今回はトノコなしで、水性コート3回

軽く研きを入れ

金ベースどぶ漬け

朱色トップ

後は墨ライン入れの後再度トップコート2回で終了です。

少しは上達できたかもです。
まとめ
やはり浮作りの出来は、見栄えも含め塗りで決まりそうです。ラッカー系の塗料は強度的には出るでしょうが、やはり室内での使用は作業中のみならず、ゴミにも強い臭いがするため家族の手前使用できないと思います。
水性塗料にあう下地材サーフェイサーと塗膜の強いコート剤探してみます。
後は試行錯誤して上達していくだけです。
次の目標としては小型化ときれいな塗装になるでしょうか。
ちなみに最近実釣に行く機会がありませんが近いうち短時間でも空き見つけて出掛けたいです。
では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。